|
| 名 前 |
 ミツバツツジ(三葉躑躅) ミツバツツジ(三葉躑躅) |
| 学 名 |
Rhododendron dilatatum var. dilatatum |
| 科 属 |
ツツジ科ツツジ属ツツジ亜属ミツバツツジ節 |
| 分 布 |
関東地方から近畿地方東部の太平洋側に分布 |
| 開花時期 |
4月~5月 |
| その他 |
落葉低木 |
|
(ミツバツツジ)2018.4@小石川植物園 |
 |
(ミツバツツジ)2014.11@小石川植物園 |
 |
ミツバツツジ(三葉躑躅)。関東地方から近畿地方東部の太平洋側に分布し、山地の尾根や岩場、里山の雑木林などに生育する落葉低木。4月~5月に美しい赤紫色の花が咲き、秋に紅葉する。雄しべの数が5本であることが特徴。ミツバツツジ群のツツジは花が終わってから枝先に三枚の葉がつく。ツツジ亜属ミツバツツジ節ミツバツツジ列。
学名:Rhododendron dilatatum var. dilatatum |
|
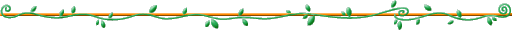 |
以下はミツバツツジ節のツツジ |
  |
 (トウゴクミツバツツジ)2012.5@小石川植物園 (トウゴクミツバツツジ)2012.5@小石川植物園 |
 |
(トウゴクミツバツツジ)2019.4@森林公園 |
 |
関東の山地に多く見られる落葉低木のトウゴクミツバツツジ(東国三葉躑躅)。ミツバツツジと違い、雄しべの数が10本あり、開花時期はやや遅く、5月~6月頃に花が咲く。ツツジ亜属ミツバツツジ節トウゴクツバツツジ列。
学名:Rhododendron wadanum |
|
  |
 (キヨスミミツバツツジ)2012.5@小石川植物園 (キヨスミミツバツツジ)2012.5@小石川植物園 |
 |
(キヨスミミツバツツジ)2025.4@小石川植物園 |
 |
キヨスミミツバツツジ(清澄三葉躑躅)。千葉県清澄山から採集され命名された。関東地方南部から近畿地方南部にかけて太平洋側に分布する。4月~5月に開花。ツツジ亜属ミツバツツジ節キヨスミミツバツツジ列。
学名:Rhododendron kiyosumense |
|
  |
 (シロバナコバノミツバツツジ)2012.4@小石川植物園 (シロバナコバノミツバツツジ)2012.4@小石川植物園 |
 |
シロバナコバノミツバツツジ(白花小葉の三葉躑躅)。本州中西部、九州に分布。ツツジ亜属ミツバツツジ節コバノミツバツツジ列。
学名:Rhododendron reticulatum var. ciliatum f. albiflorum |
|
  |
 (ナンゴクミツバツツジ)2012.4@小石川植物園 (ナンゴクミツバツツジ)2012.4@小石川植物園 |
 |
ナンゴクミツバツツジ(南国三葉躑躅)。九州に分布。ツツジ亜属ミツバツツジ節キヨスミミツバツツジ列。
学名:Rhododendron mayebarae |
|
  |
 (トサノミツバツツジ)2007.4@小石川植物園 (トサノミツバツツジ)2007.4@小石川植物園 |
 |
トサノミツバツツジ(土佐三葉躑躅)。岐阜、滋賀、紀伊半島、四国全域に生育する。ツツジ亜属ミツバツツジ節ミツバツツジ列。
学名:Rhododendron dilatatum subsp. decandrum f. decandrum |
|
  |
 (アワノミツバツツジ)2003.4@小石川植物園 (アワノミツバツツジ)2003.4@小石川植物園 |
 |
アワノミツバツツジ(阿波の三つ葉躑躅)。四国の山地に分布。ツツジ亜属ミツバツツジ節ミツバツツジ列。
学名:Rhododendron inobeanum |
|
  |
 (サイゴクミツバツツジ)2018.4@小石川植物園 (サイゴクミツバツツジ)2018.4@小石川植物園 |
 |
サイゴクミツバツツジ(西国三葉躑躅)。九州中部の山地に生える。ツツジ亜属ミツバツツジ節サイゴクミツバツツジ列。
学名:Rhododendron nudipes |
|
  |
 (ハヤトミツバツツジ)2007.3@小石川植物園 (ハヤトミツバツツジ)2007.3@小石川植物園 |
 |
(ハヤトミツバツツジ)2018.4@小石川植物園 |
 |
鹿児島県原産で低山地の岩場に多く見られる落葉低木のハヤトミツバツツジ(隼人三葉躑躅)。2月下旬から3月に葉のない枝先に淡い赤紫色の花が元気に咲き出す。別名はイワツツジ(岩躑躅)。ツツジ亜属ミツバツツジ節ミツバツツジ列。
学名:Rhododendron dilatatum subsp. satsumense var. satsumense |
|
  |
 (タカクマミツバツツジ)2007.4@小石川植物園 (タカクマミツバツツジ)2007.4@小石川植物園 |
 |
タカクマミツバツツジ(高隈三葉躑躅)。九州南部の霧島山、高隈山に分布。ツツジ亜属ミツバツツジ節タカクマミツバツツジ列。
学名:Rhododendron viscistylum |
|
  |
 (ヤクシマミツバツツジ)2006.5@小石川植物園 (ヤクシマミツバツツジ)2006.5@小石川植物園 |
 |
ヤクシマミツバツツジ(屋久島三葉躑躅)。屋久島の固有種で、高地に自生する。ツツジ亜属ミツバツツジ節サイゴクミツバツツジ列。
学名:Rhododendron yakumontanum |
|
  |
 (ヒダカミツバツツジ)2007.4@小石川植物園 (ヒダカミツバツツジ)2007.4@小石川植物園 |
 |
ヒダカミツバツツジ(三葉躑躅)。北海道日高地方に分布。ツツジ亜属ミツバツツジ節ミツバツツジ列。
学名:Rhododendron dilatatum subsp. dilatatum var. boreale |
|
  |
 (オンツツジ)2012.4@小石川植物園 (オンツツジ)2012.4@小石川植物園 |
 |
(オンツツジ)2012.12@小石川植物園 |
 |
オンツツジ(雄躑躅)。紀伊半島、四国、九州に広く分布。ツツジ亜属ミツバツツジ節オンツツジ列。春に鮮やかな赤紫色の花が咲き、晩秋には赤く紅葉します。
学名:Rhododendron weyrichii |
|
  |
 (タンナアカツツジ)2012.4@小石川植物園 (タンナアカツツジ)2012.4@小石川植物園 |
 |
タンナアカツツジ(耽羅赤躑躅)。韓国の済州島に分布し、山地に生える。「耽羅」というのは済州島の古名です。オンツツジの別名。ツツジ亜属ミツバツツジ節オンツツジ列。
学名:Rhododendron weyrichii |
|
  |
 (ムラサキオンツツジ)2019.4@小石川植物園 (ムラサキオンツツジ)2019.4@小石川植物園 |
 |
(ムラサキオンツツジ)2006.4@小石川植物園 |
 |
(ムラサキオンツツジ)2011.12@小石川植物園 紅葉 |
 |
ムラサキオンツツジ(紫雄躑躅)。オンツツジの希少種で、紀伊半島にのみ分布する。ツツジ亜属ミツバツツジ節オンツツジ列。
学名:Rhododendron weyrichii var. purpuriflorum |
|
  |
 (ジングウツツジ)2024.4@小石川植物園 (ジングウツツジ)2024.4@小石川植物園 |
 |
ジングウツツジ(神宮躑躅)。東海地方の蛇紋岩地帯に生息する落葉低木のツツジ。伊勢神宮の神域から発見されたことから和名が由来。浜松市内の渋川に群生地があるため、シブカワツツジ(渋川躑躅)の別名あり。春に気品ある花を咲かせることから庭木として利用される。ツツジ亜属ミツバツツジ節オンツツジ列。
学名:Rhododendron sanctum |
|
|